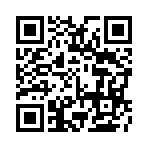2014年09月25日
御幣等の裁断
祭り時期になると 神社の注連縄に付ける紙垂(しで)やら御幣の裁断が半端なく続きます。

写真のカラフルな御幣は 獅子頭に付ける御幣です。
これだけでも 150枚ほどあります
これは 一組の分です。
獅子組さん 四組あるので この数の4倍
折っては切り 折っては切り の繰り返し
全体を通して 数を数えたことはありませんが
用紙の大きさは千差万別
すべて合わせると 毎年 1000枚以上は切っていると思いますが・・・・(汗)
この秋も仕事の合間に 各種の紙垂や御幣を裁断していますが
ずっと カッターで切れ目を入れているので 案の定 今年も 手首が痛くなりました。
写真のカラフルな御幣は 獅子頭に付ける御幣です。
これだけでも 150枚ほどあります

これは 一組の分です。
獅子組さん 四組あるので この数の4倍
折っては切り 折っては切り の繰り返し
全体を通して 数を数えたことはありませんが
用紙の大きさは千差万別
すべて合わせると 毎年 1000枚以上は切っていると思いますが・・・・(汗)
この秋も仕事の合間に 各種の紙垂や御幣を裁断していますが
ずっと カッターで切れ目を入れているので 案の定 今年も 手首が痛くなりました。
2014年09月25日
秋の社日
昨日は 秋の社日でした。
社日とは・・・
春分(3月21日頃)と秋分(9月23日頃)に最も近い戊(つちのえ)の日を「社日」といいます。
春の社日は「春社」、秋の社日は「秋社」とも呼ばれ、土地の神様をまつる日とされています。
春の社日の頃は種まきの時期にあたり、秋の社日の頃は収穫の時期にあたります。
そのため社日は重要な節目と考えられ、春は五穀の種子を供えて豊作を祈り、秋は初穂を供えて収穫を感謝するようになりました。
「土」という意味がある「戊」の日に豊作祈願をするもので、「社」とは土地の守護神のことを表しています。
社日は「土の神」をまつるので、この日は農作業など、土をいじることを忌む風習が各地に見られます。
社日は、その土地ごとの神様を祝うので行事の形は様々です。
香川県では 地神(じじん)さんと呼ばれている所で
祭事を行うのが 一般的ではないでしょうか!

時代も変わったのでしょう。
専業の農家の方が少なくなったためか 祭事も簡略化していく傾向にあります。
古くは、社日の祭事は 必ず その当日に行っていましたが
最近は ほとんどが 土日祭日に行われます。
社日の日でも農作業をなさっている方も多く見受けられます。
古い風習慣習が 徐々に廃れていくのは 何か寂しい気がしますね。
社日とは・・・
春分(3月21日頃)と秋分(9月23日頃)に最も近い戊(つちのえ)の日を「社日」といいます。
春の社日は「春社」、秋の社日は「秋社」とも呼ばれ、土地の神様をまつる日とされています。
春の社日の頃は種まきの時期にあたり、秋の社日の頃は収穫の時期にあたります。
そのため社日は重要な節目と考えられ、春は五穀の種子を供えて豊作を祈り、秋は初穂を供えて収穫を感謝するようになりました。
「土」という意味がある「戊」の日に豊作祈願をするもので、「社」とは土地の守護神のことを表しています。
社日は「土の神」をまつるので、この日は農作業など、土をいじることを忌む風習が各地に見られます。
社日は、その土地ごとの神様を祝うので行事の形は様々です。
香川県では 地神(じじん)さんと呼ばれている所で
祭事を行うのが 一般的ではないでしょうか!
時代も変わったのでしょう。
専業の農家の方が少なくなったためか 祭事も簡略化していく傾向にあります。
古くは、社日の祭事は 必ず その当日に行っていましたが
最近は ほとんどが 土日祭日に行われます。
社日の日でも農作業をなさっている方も多く見受けられます。
古い風習慣習が 徐々に廃れていくのは 何か寂しい気がしますね。